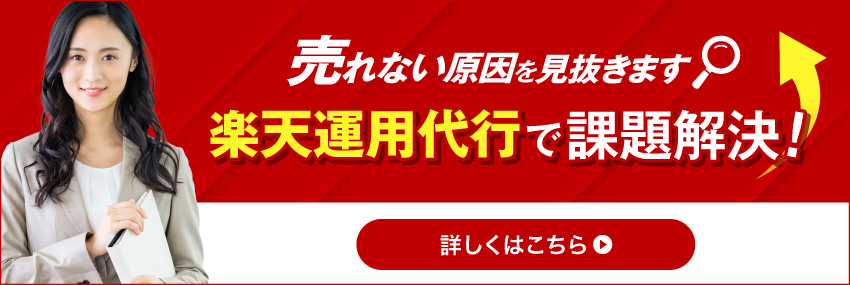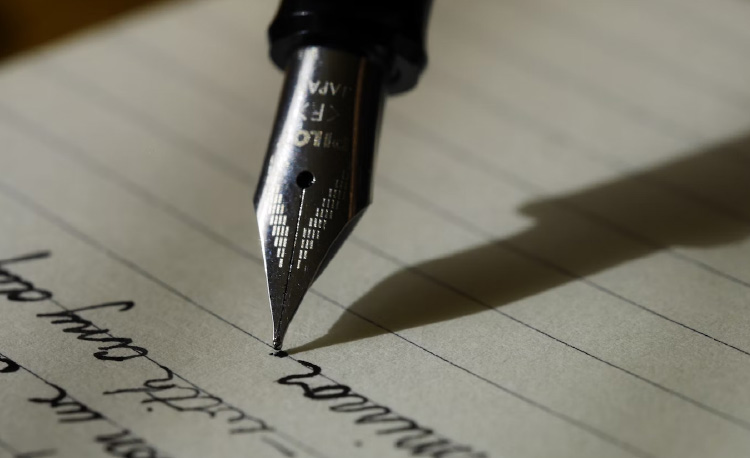ECは消費者のライフスタイルの変化やテクノロジーの進化によって、大きな転換期を迎えています。とくにコロナ禍以降、オンラインで購入することが一般的になり、ECの重要性は一気に高まりました。しかし現状では、食品業界についてのEC化率は、ほかの分野に比べて低く、とりわけ課題の多い領域でもあります。
経済産業省の「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」では、2023年の物販系BtoC-EC市場規模は14兆6,760億円、うち「食品・飲料・酒類」は2兆9,299億円とされています。さらに同調査によると、食品分野のEC化率は4.29%であり、物販系全体の平均(9.38%)を大きく下回っています。
出典URL: https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/statistics/index.html
本記事では、日本の食品EC市場の現状や、なぜEC化が遅れているのか、その背景をわかりやすく解説します。また、楽天市場やAmazonなどの主要プラットフォームにおける動向を紹介しつつ、食品業界がいまECに挑戦すべき理由や、将来の成長可能性についても掘り下げていきます。
食品業界のEC化率が低い理由
鮮度や品質への不安と消費者心理
食品、とくに生鮮品に関しては、「自分の目で見て選びたい」という消費者の心理が根強くあります。写真や説明だけでは品質を完全に判断できないため、ECでの購入に不安を感じる人が少なくありません。こうした心理的ハードルが、食品ECの普及を妨げる大きな要因となっています。
高コストな物流と価格競争の壁
冷蔵や冷凍が必要な食品は、クール便による配送コストが高額になりやすい特徴があります。このコストは最終的に商品価格に反映されるため、実店舗と比べて割高に感じられることがあります。その結果、ECでは価格面での競争力を維持しづらく、参入をためらう企業も少なくありません。
実店舗の利便性と購買習慣
日本はスーパーやコンビニが全国に広く存在し、仕事帰りや買い物のついでに食品を購入できる環境が整っています。「ついで買い」のできる利便性が高いため、あえてECを利用する必然性を感じにくいのが現状です。こうした購買習慣の強さもまた、食品分野でのEC化が進みにくい背景となっています。
主要ECプラットフォームの食品動向
楽天市場における食品カテゴリの特長
楽天市場は、ギフトやお取り寄せグルメに強みを持っています。とくに地域の特産品や有名店のスイーツなど、特別感のある食品が人気です。さらに、楽天ポイントを活用した販促施策により、リピーターを獲得しやすいのが特長です。こうした仕組みが、食品ECにおける楽天市場の優位性を支えています。
食品分野全体ではEC化率が他業界に比べてまだ低いものの、楽天市場における食品カテゴリの売上は年々伸びており、今後の拡大余地が大きいといえます。こうした成長性と仕組みが、食品ECにおける楽天市場の優位性を支えています。
Amazonの利便性と食品定期購入の拡大
Amazonは、プライム会員向けの迅速な配送サービスや「定期おトク便」を通じて、日常的な食品購入のニーズを取り込んでいます。水やお米、調味料といった定番商品は特に人気で、利便性を重視する消費者層に支持されています。結果として、食品ECにおいてもAmazonは生活インフラ的な立ち位置を確立しています。
Yahoo!ショッピングとポイント経済圏の強み
Yahoo!ショッピングは、PayPayとの強力な連携により、ポイント還元率の高さを武器にしています。とくにソフトバンクユーザーやPayPayユーザーに強く訴求でき、購買意欲を高める効果を発揮しています。消費者は「お得に買える場」として認識しており、食品カテゴリでもその強みを発揮しています。

消費者行動の変化と新しい潮流
巣ごもり需要から日常利用への定着
コロナ禍を契機に広がった食品EC利用は、単なる「巣ごもり需要」にとどまりませんでした。現在では、野菜や肉、加工食品といった日常的な食材の購入が増え、ECが生活の一部として定着しつつあります。
健康志向・特定ニーズ食品の需要増加
消費者の間では、オーガニック食品や無添加食品、プラントベースフードなど、健康やライフスタイルに配慮した商品への関心が高まっています。こうした商品は実店舗では品ぞろえが限られることもありますが、ECなら全国から簡単に入手できるため需要が拡大しています。
食品ECの成長可能性と今後の展望
冷凍技術・プレミアムフローズン食品の拡大
食品ECの拡大を支える要素のひとつが、冷凍技術の進化です。レストランの味を再現した高品質な冷凍食品、いわゆる「プレミアムフローズン」が人気を集めています。長期保存が可能なため、フードロス削減にもつながり、事業者と消費者の双方にメリットをもたらしています。
D2Cと地方創生への期待
近年では、生産者やメーカーが消費者に直接商品を届けるD2C(Direct to Consumer)モデルが注目を集めています。生産者の顔や想いを伝えることで、消費者とのつながりを深められるのが特長です。さらに、地方の隠れた逸品を全国に届けることができ、地方創生の一助にもなっています。
食品業界がいまECに挑戦すべき理由
EC化で広がる販路と顧客接点
食品業界がECに取り組む最大のメリットは、販路を全国・海外へと拡大できることです。従来の店舗販売や地域の卸売だけでは届かなかった顧客層に、自社の商品を届けられます。さらに、オンライン上での購入履歴やレビューを通じて、顧客との関係性を深められる点も魅力です。
成長市場に参入するチャンス
食品分野のEC化率は依然として低い水準ですが、裏を返せば成長余地が非常に大きい市場です。物流や冷凍技術の発展、消費者の購買習慣の変化によって、今後はさらにEC利用が拡大すると予測されます。つまり、早めに参入した企業ほど先行者メリットを享受できるチャンスがあるのです。
課題解決に向けた支援サービスの活用
食品業界特有の課題である物流コストや品質不安も、近年では多様な支援サービスによって解決が進みつつあります。ECモールや専門業者と連携することで、自社単独では難しい課題も克服できます。こうした環境の変化を踏まえると、いまこそ食品業界がECに挑戦すべき好機だといえるでしょう。
まとめ
食品業界のEC化率はまだ低い水準にとどまっていますが、そこには大きな成長余地とチャンスがあります。鮮度や物流コストといった課題も、技術やサービスの進化によって克服できるようになりつつあり、いまこそ食品業界がECに取り組むべきタイミングです。
とはいえ、「自社の商品はECに向いているのか?」「どんな成功・失敗事例があるのか?」といった疑問を持つ企業も多いのが実情です。
ベイクロスマーケティングでは、食品業界をはじめとするさまざまな事業者様のEC運営代行・サイト改善支援を行っています。戦略設計からサイト構築、運営、集客施策まで一貫してサポートいたしますので、自社だけでは不安という方も安心してご相談ください。
ECに挑戦するなら「いま」から。ぜひお気軽にお問い合わせください。
Written by
koyama 
ECサイト構築・モール出店の新着記事
サービス一覧
楽天市場のノウハウとテクニック満載
キャプテンEC